〜行政書士・税理士・社労士・司法書士の先生必見〜
「何を話せばいいかわからない」「撮影を始めたら話が脱線してしまう」——これは行政書士や税理士、社労士、司法書士など、士業の先生からよく聞く悩みです。動画を始めたいと思っても、カメラの前に立つと順序がバラバラになったり、話が長くなりすぎたりして、撮り終えた後に「これで良かったのだろうか」と不安になることはありませんか?
実は、動画の出来栄えは撮影前の台本作りで8割が決まります。
台本があれば話の流れが整理され、視聴者にとっても聞きやすく、編集もスムーズになります。反対に、準備不足のまま撮影すると情報が散らばり、視聴者が途中で離脱する原因になってしまいます。
士業の動画は専門性が高い分だけ、内容が複雑になりがちです。相続税申告や許認可申請などを一度に全て説明しようとすれば10分以上になり、情報量は多くても印象に残らないこともあります。だからこそ、「何を」「どの順番で」「どのくらいの時間で」話すのかを明確に決めることが不可欠です。
本記事では、行政書士・税理士・社労士・司法書士などの士業の先生がすぐに活用できる動画シナリオ台本テンプレートをご紹介します。これを使えば、初めての撮影でもブレずに話せ、視聴者の信頼を短時間で獲得できるようになります。

1. 士業動画の台本が重要な理由
士業が動画で成果を出すためには、まず「台本作り」が欠かせません。
これは行政書士・税理士・社労士・司法書士など、どの分野でも共通です。専門性の高いテーマこそ、事前の設計が視聴者の満足度を大きく左右します。
1|話の順序が整理される
台本を用意する最大のメリットは、撮影中の迷いや沈黙を防げることです。
テーマを決めていても、カメラの前に立つと緊張で話が前後したり、言葉に詰まったりすることは珍しくありません。あらかじめ「結論→理由→具体例→まとめ」という流れを台本に落とし込むことで、短時間で要点を正しく伝えられます。
2|視聴者の離脱を防ぐ
動画は最初の30秒で視聴者の興味をつかめなければ、すぐに離脱されます。
台本があると情報の過不足を防ぎ、視聴者が知りたい順番で話せるため、最後まで見てもらえる確率が高まります。たとえば税理士が「相続税の節税方法」を説明する場合でも、最初に結論とメリットを提示してから具体例を話すことで、視聴者の集中を保てます。
文章構造が明確なので見出しを付けやすく、行政書士なら「許認可申請の流れ」、社労士なら「労務管理のポイント」など、キーワードを自然に含められます。動画とブログを連動させれば、検索流入とYouTube流入の両方から見込み客を獲得できます。
つまり、台本は単なる原稿ではなく、視聴者の理解を助け、SEO効果を高め、成果に直結するための設計図です。
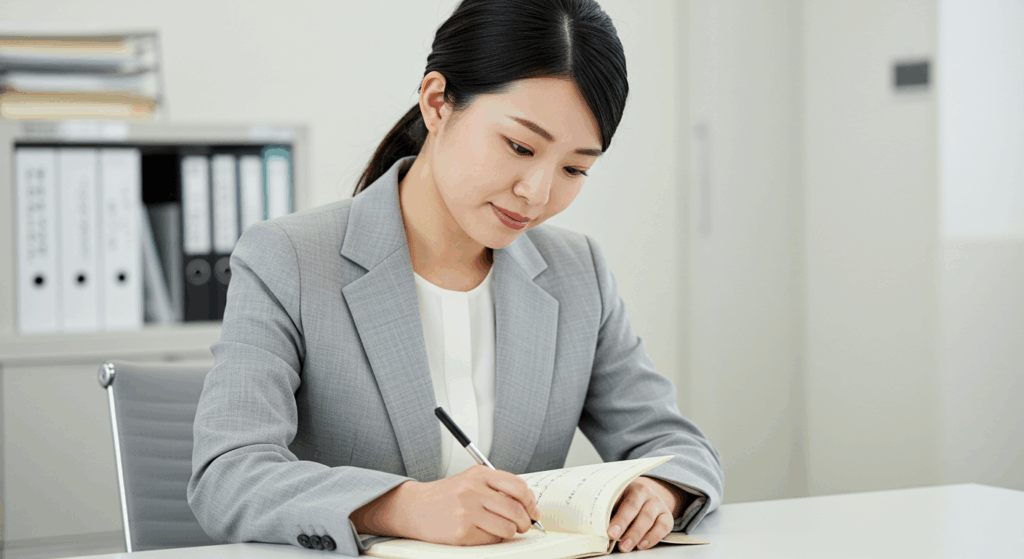
2. 基本構成「PREP法+CTA」
士業が動画で成果を上げるためには、「話の組み立て方」が非常に重要です。
その中でも、行政書士・税理士・社労士・司法書士といった専門職が特に取り入れやすく、かつ視聴者にとっても理解しやすいのがPREP法です。これは「Point(結論)→Reason(理由)→Example(具体例)→Point(結論)」という流れで話す方法で、短時間でも説得力のある説明ができます。
さらに、動画の最後には必ずCTA(Call To Action)=行動喚起を入れることが鉄則です。「初回相談はこちら」「詳細はブログ記事へ」など、視聴者が次に取るべき行動を明確に示すことで、動画を単なる情報提供で終わらせず、問い合わせや面談予約につなげられます。
PREP法の例
テーマ:「相続手続きの注意点」
- 結論(Point)
「相続では“期限”を守ることが最重要です」 - 理由(Reason)
「期限を過ぎると税負担が増えたり、相続放棄ができなくなります」 - 具体例(Example)
「例えば、あるご家庭では遺産分割協議が長引き、10カ月の申告期限を超えてしまった結果、余分な税金を支払うことになりました」 - 結論(Point)
「期限管理のためにも、早めに専門家へ相談を」 - CTA(行動喚起
「概要欄のリンクから初回30分無料相談をご利用ください」
この流れは相続だけでなく、
- 行政書士なら「建設業許可の取得条件」
- 税理士なら「節税のための経費計上のルール」
- 社労士なら「労務管理の法改正ポイント」
- 司法書士なら「不動産登記の流れ」
といったテーマにも応用可能です。
PREP法を使うと、冒頭で結論を提示するため視聴者が「この動画で何が得られるのか」をすぐ理解でき、離脱を防げます。そして最後のCTAで行動を促せば、見込み客が次のステップに進みやすくなります。
台本にこの構成を組み込むことは、士業動画を「見られるだけ」から「成果につながるツール」へ変える大きな一歩です。

3. 士業向け動画台本テンプレート
① FAQ解説型(3〜4分)
【オープニング(10〜15秒)】
・質問提示+自己紹介
「〇〇の手続きって、どのくらいの期間で終わるんですか?」
「相続税の申告期限っていつまでですか?」
「労務管理の法改正、何から手をつければいいですか?」
こうした“視聴者が実際に抱く質問”を冒頭で提示します。次に短く自己紹介を加えます。
例:「こんにちは、〇〇(職種)の△△です。今日はこの質問にお答えします。」
【本編(約2分)】
1. 結論(まず答えを提示)
視聴者が知りたい答えを最初に明確に伝えます。例:「相続税の申告期限は、亡くなられてから10カ月以内です」。
2. 理由(なぜそれが大切か)
根拠や背景を説明します。例:「期限を過ぎると加算税や延滞税がかかる可能性があるからです」。
3. 具体例(数字・事例)
過去のケースや統計を交えて、視聴者が状況をイメージしやすい形で示します。例:「以前の案件では、準備に2週間、審査に30日かかりました」。守秘義務に配慮しつつリアリティを出します。
【まとめ(20秒)】
・結論の再提示:「〇〇の手続きは期限を守ることが何より重要です」
・CTA(行動喚起):「概要欄のリンクから初回無料相談をご利用ください」「関連ブログで詳細を解説しています」など、具体的な次の行動を促す。この“質問から始まるFAQ解説型”は、行政書士、税理士、社労士、司法書士、弁護士などあらゆる士業で活用できます。
視聴者の興味を瞬時につかみ、短時間で信頼感を築き、問い合わせへと導くための汎用性の高い構成です。
② 事例紹介型(5分)
【オープニング(15〜20秒)】
・案件概要を簡潔に紹介(匿名化)
例:「今回は、実際に対応した〇〇の事例をご紹介します。個人情報保護のため、詳細は一部変更していますが、全体の流れやポイントはそのままお伝えします。」
冒頭で事例のテーマや成果を予告することで、視聴者が「自分にも当てはまるかも」と関心を持ちやすくなります。
【本編(約3〜4分)】
1. 依頼前の状況
依頼者が抱えていた悩みや背景を具体的に説明します。例:「許可申請の期限が迫っており、必要書類の準備が進んでいない状態でした」。
2. 課題
何が障害となっていたのかを明確にします。「複雑な要件を理解できず、書類不備が複数あった」など。
3. 解決策
専門家としてどのような方針・方法を取ったのかを説明。ステップごとに整理すると分かりやすいです。
4. 結果(数値で示す)
成果は必ず数字や期間で示します。例:「申請から15日で許可取得」「追加費用ゼロで解決」。
5. 学び(視聴者が参考にできるポイント)
視聴者が自分の状況に置き換えられるよう、再現性のあるアドバイスを添えます。
【まとめ(20〜30秒)】
・同様のケースで悩む方への一言:「期限が迫っていても、正しい手順を踏めば解決できます」など。
・CTA(行動喚起):「概要欄のリンクから無料相談を予約してください」「関連ブログ記事で詳細解説を公開中です」。この事例紹介型は、行政書士、税理士、社労士、司法書士、弁護士など、士業全般で使える強力なフォーマットです。
ストーリー性があるため信頼を高めやすく、問い合わせにも直結しやすい構成です。
③ セミナー・勉強会切り抜き型(1〜2分)
【オープニング(15〜20秒)】
・セミナー全体のテーマを簡単に触れた後、「このセミナーで最も多かった質問」を提示します。
例:「今回のセミナーでは、相続手続きに関するご質問を多くいただきました。その中で特に多かったのが『期限内に申請するための最短ルート』です。」
こうすることで、視聴者は「この動画を見れば自分の疑問が解決する」と期待できます。
【本編(約2〜3分)】
・質問と回答部分を短く抽出し、要点は2〜3つに絞ります。
例:
1. 結論を先に述べる:「申請には最低〇日必要です」
2. 理由を簡潔に説明:「必要書類の取得に時間がかかるためです」
3. 補足のアドバイス:「休日を挟むとさらに日数が延びるため、余裕を持って準備しましょう」
・士業(行政書士、税理士、社労士、司法書士、弁護士など)の場合、専門用語は簡単な言葉に置き換え、図や例え話を交えると理解度が高まります。
【まとめ(20〜30秒)】
・回答の要点をもう一度整理して繰り返すことで、視聴者の記憶に残りやすくなります。
・「続きはフル動画やブログで詳細を解説しています」などの案内で深掘りコンテンツへ誘導。
・CTA(行動喚起):「概要欄のリンクから無料相談をお申し込みください」「関連ページで最新の手続き情報をご覧いただけます」など、具体的な行動に導きます。このセミナー切り抜き型は、情報量をコンパクトにまとめつつ、興味を持った視聴者を次の行動へスムーズに誘導できる構成です。

4. 士業が台本を作る際の注意点
士業が動画台本を作る際には、いくつかの重要なポイントを押さえることで、視聴者の理解度や信頼感を大きく高められます。
1|士業の動画制作の台本は、専門用語は中学生レベルの言葉に置き換える
行政書士・税理士・社労士・司法書士といった士業は、日常的に専門用語を使いますが、視聴者の多くはその分野の初心者です。例えば「遺産分割協議書」は「相続人全員で話し合った内容をまとめた書類」と言い換えるだけで理解度が上がります。専門用語は解説を添えるか、平易な言葉に置き換えることを意識しましょう。
2|士業の動画制作の台本は、1動画1テーマに絞る
一度に複数のテーマを扱うと情報が詰め込みすぎになり、視聴者は途中で混乱します。テーマは1本に1つに絞り、そのテーマに沿って構成することが重要です。例えば「建設業許可の申請方法」と「更新の手続き」は別々の動画にする方が、最後まで視聴してもらいやすくなります。
3|士業の動画制作の台本は、数字と期限を必ず入れる
「できるだけ早く」よりも「申請期限は〇日以内」「手続きは最短3日」といった具体的な数字を提示した方が、信頼感と行動意欲が高まります。士業の業務は期限や日数が明確なものが多いので、数値情報は積極的に盛り込みましょう。
4|士業の動画制作の台本は、CTAは具体的に
動画の最後には必ず次の行動を示すCTA(Call To Action)を入れます。「概要欄のリンクから30分無料相談へ」「関連ブログ記事で詳しく解説しています」など、視聴者が迷わず行動できるように具体的に案内します。漠然と「お問い合わせください」ではなく、リンク先や方法まで明示することで、コンバージョン率が向上します。
これらを意識するだけで、士業の動画は「情報発信」から「信頼獲得と集客」に進化します。
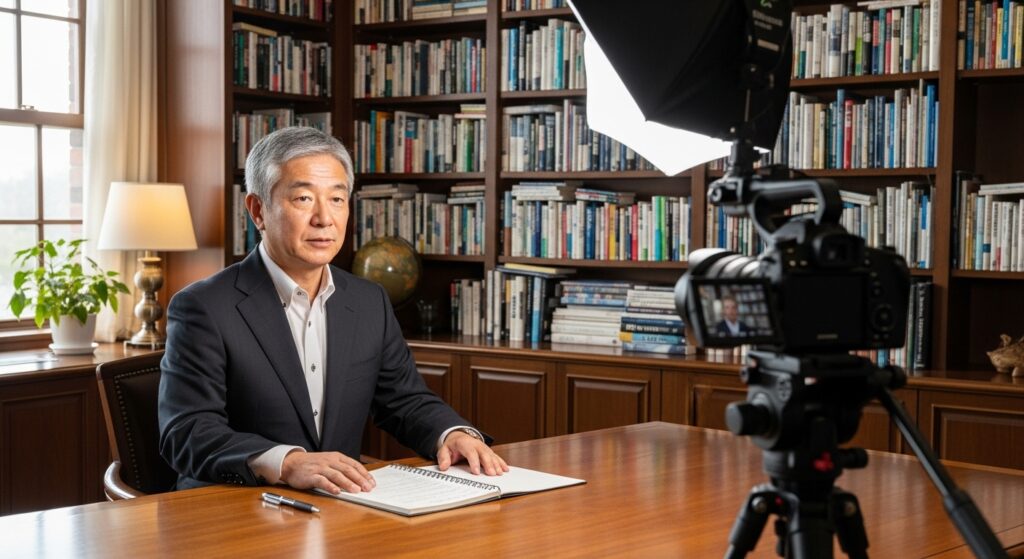
5. 配信用の動画台本からブログ化までの流れ
動画台本は撮影だけでなく、ブログ記事の原稿としてもそのまま活用できます。
動画とブログを連動させれば、YouTubeからの流入とGoogle検索からの流入を同時に獲得でき、集客効果が倍増します。以下の手順で進めると効率的です。
1|台本を元に撮影
事前に台本を用意しておくことで、撮影時間の短縮と話のブレ防止が可能になります。士業の場合、正確さが求められるため、数字や期限など事実確認を済ませてから収録しましょう。
2|文字起こしを行う
撮影後、動画の音声を文字起こしします。YouTubeの自動字幕機能やAI文字起こしツールを使えば、ほぼ自動化が可能です。文字化することで、SEOに有効な記事のベースが整います。
3|ブログ記事として再構成
文字起こしした文章を読みやすい形に整えます。見出し(h2・h3)を付け、SEOキーワード(例:「行政書士 建設業許可」「税理士 相続税 申告期限」)を自然に含めます。余分な口語表現は削除し、必要に応じて図解や箇条書きを加えると、記事としての完成度が高まります。
4|動画を埋め込み
記事内の冒頭または要点部分に動画を埋め込みます。ブログ読者の中には動画派も多く、両方を用意することで滞在時間と満足度が向上します。
5|内部リンクとCTAを設置
記事の最後に、関連する別記事やサービスページへのリンクを配置します。「この内容の詳細は無料相談で解説」「関連する事例はこちら」など、読者が次の行動を取りやすい導線を用意しましょう。
この流れを習慣化すれば、1本の動画から複数の集客資産(YouTube動画、ブログ記事、SNS投稿)が生まれ、士業の集客基盤が短期間で強化されます。

士業の先生方へ|集客を加速させたいなら動画が必須
株式会社ANDAZは、士業の先生方に特化した動画制作・YouTube制作・SNS動画制作をワンストップで提供します。
サービス内容
- 企画立案(ポジショニング戦略設計)
- 対談・セミナー・インタビュー撮影
- YouTube用長尺動画編集
- SNS用ショート動画制作
- サムネイル・タイトル設計(SEO対応)
過去には、税理士、公認会計士、弁護士、中小企業診断士など、多くの士業動画を手がけてきました。各士業ごとの特性や視聴者層を理解し、最適な形でコンテンツを制作します。
継続的に動画を更新できる仕組みを作りたいと思っている士業の先生方、ぜひともお声がけください。
一緒に、“選ばれる士業”への第一歩を踏み出しましょう!

