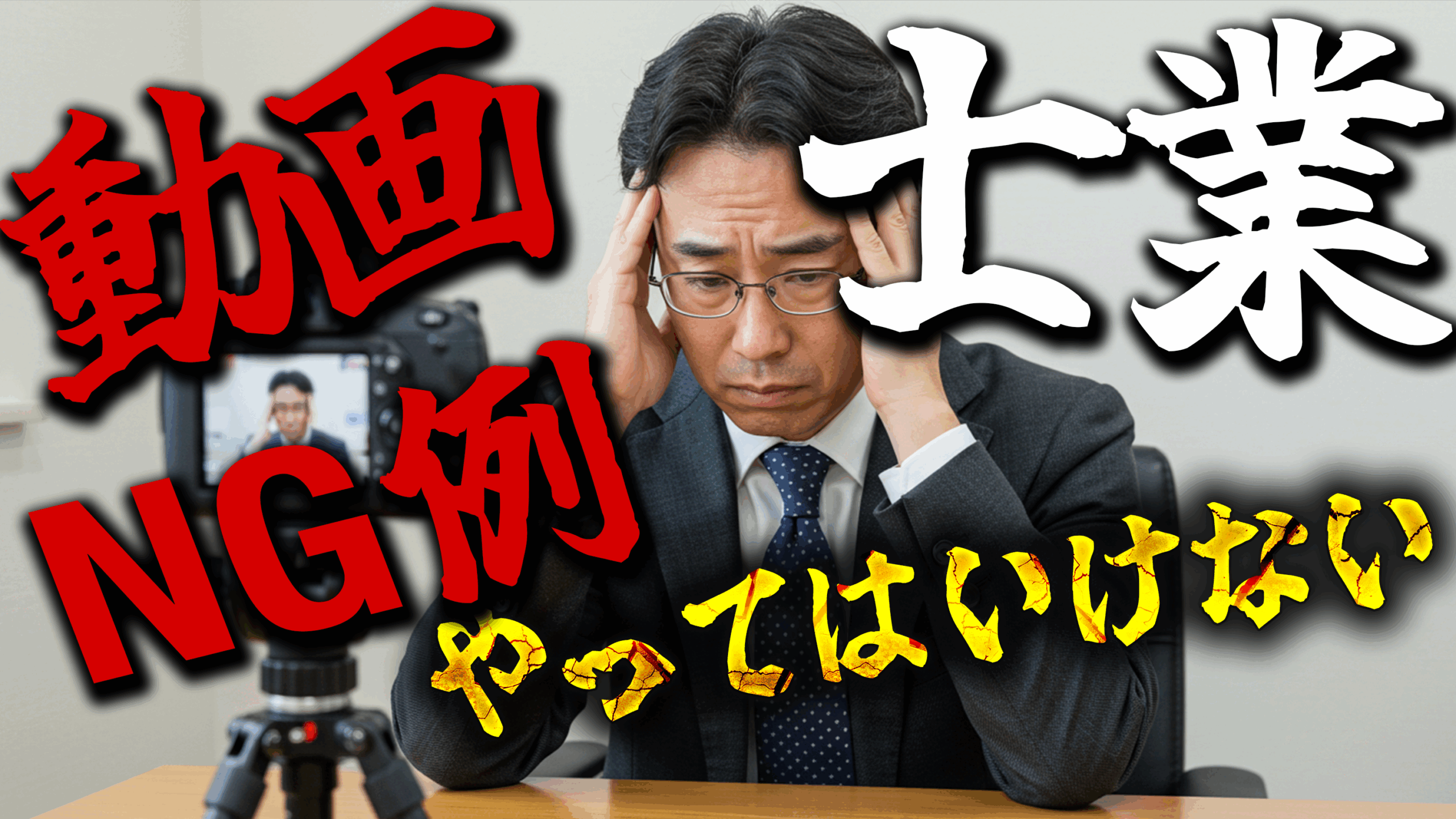「士業がやってはいけない動画の3大NG例|信頼を落とさないために押さえるべきポイント」
士業の動画活用が急増する中で起きている「失敗の共通点」とは?
ここ数年、士業や先生業の方が動画を活用するケースが急速に増えています。
弁護士、司法書士、税理士、社労士、行政書士などの先生方が「顧客に自分の専門性を伝えたい」「セミナーや勉強会の内容を広く届けたい」「Webから新しい相談者を獲得したい」という思いから、YouTubeやSNSでの情報発信を始めるケースが後を絶ちません。
実際、動画制作の現場でも、士業の先生からのYouTube制作依頼や動画マーケティングに関するご相談が増え続けています。コロナ禍をきっかけに対面での営業活動が制限される中、デジタルを活用した情報発信の重要性がより一層高まったことも背景にあるでしょう。
しかし実際にお話を伺うと、動画を始めた士業の先生からよく聞くのが”失敗談”です。「頑張って撮ったのに見られない」「逆に信頼を落とした気がする」「時間ばかりかかって成果が出ない」「動画制作に投資したのに問い合わせが増えない」といった声が数多く寄せられます。
動画は正しく活用すれば強力な武器になりますが、やり方を間違えると逆効果になることもあります。特に士業は「信頼」が最も重要な要素であるため、動画でマイナス印象を与えてしまうと、取り返すのに時間がかかってしまいます。
そこで今回は、士業がやってはいけない動画の3大NG例を取り上げます。これらを避けるだけで、あなたの動画は一気に「信頼を生むコンテンツ」に変わり、YouTube制作や動画制作の投資対効果を大幅に向上させることができるでしょう。
【NG例1】第一印象を壊すNG:暗い映像・聞き取りにくい音声
なぜ映像品質が士業にとって致命的なのか
人は出会って3秒で相手の印象を判断するといわれています。
これは動画にも当てはまり、特に士業のYouTube制作では初見の印象が成約に直結します。映像が暗い、顔がはっきり見えない、音声がこもって聞き取りにくい――こうした状況では、視聴者はすぐに離脱してしまいます。
特に士業は「信頼感」が命です。法的な問題や重要な手続きを任せる相手を選ぶ際、顧客は慎重になります。映像が暗いだけで「この先生は頼りないかもしれない」「きちんと仕事をしてくれるだろうか」と感じられてしまうのです。
逆に、明るい表情とクリアな声が伝わるだけで、相手は自然と安心し、話を聞く姿勢になってくれます。これは対面相談と同じ心理メカニズムが働いているためです。
よくある技術的な失敗パターン
動画制作を始めたばかりの士業の先生に多い失敗例をご紹介します。
- 自然光だけに頼って夕方や曇りの日に撮影:時間帯や天候に左右されて、顔が影になったり暗く映ったりする
- スマートフォンの内蔵マイクのみで録音:エアコンの音や外の雑音が入り、声がこもって聞き取りにくくなる
- 逆光での撮影:窓を背にして撮影すると、顔が暗くシルエット状態になってしまう
- 画質設定が不適切:YouTubeに最適化されていない解像度やフレームレートで撮影している
これらの問題は、動画制作の基本的な知識があれば簡単に解決できるものばかりです。
具体的な解決策
最低限のライティングとマイクを整えることが必須です。高額な機材は必要ありません。
照明に関する改善策:
- 窓の正面に座って自然光を活用する(朝10時〜午後2時頃がベスト)
- リングライトやLEDライト(3000円〜1万円程度)を1つ導入する
- 白い壁や白いボードを反射板代わりに使って顔を明るく見せる
- 蛍光灯の真下は避ける(影ができやすいため)
音声に関する改善策:
- イヤホンマイクや外付けマイク(5000円〜2万円程度)を使って声をクリアにする
- 録音前にマイクテストを必ず行う
- エアコンや冷蔵庫などの生活音が入らない環境を選ぶ
- 声の大きさは普段より2割程度大きめを意識する
これだけで動画の印象は大きく変わり、先生の誠実さや専門性がきちんと伝わるようになります。YouTube制作において、この基本的な品質確保は絶対に軽視してはいけない要素です。
【NG例2】信頼を損なうNG:だらだら話す・要点がない
なぜ冗長な説明が士業の動画で致命的なのか
動画でよくあるのが、「話が長い」「結局何を言いたいのかわからない」という失敗です。専門家は知識が豊富な分、つい説明が長くなりがちです。
しかし視聴者の集中力は数分しか続かず、特にYouTubeでは最初の15秒で約20%の視聴者が離脱するというデータもあります。
だらだらと話してしまうと、「この先生は結局自分にとって必要な情報をくれない」「要点を整理して話せない人なのかもしれない」と思われ、信頼を損なってしまいます。これは実際の相談でも同様で、要点を簡潔に伝えられない専門家は信頼度が下がってしまうのです。
士業の動画でありがちな構成上の問題
動画制作において、多くの士業の先生が陥りがちな問題を整理してみましょう。
- 自己紹介に5分以上かける:視聴者は先生のプロフィールより、自分の問題解決を求めている
- 専門用語の説明が長すぎる:必要以上に詳しく説明して本題になかなか入らない
- 結論を最後まで言わない:「続きは次回」といった構成で視聴者をイライラさせる
- 一つの動画で複数のテーマを扱う:税務と労務など、関連はあるが別々のテーマを同時に話してしまう
これらは全て、視聴者の期待と実際のコンテンツとの間にギャップを生む原因となります。
シナリオ設計の重要性
解決策として、シナリオをあらかじめ設計することが大切です。YouTube制作において、台本作りは成功の鍵を握っています。
効果的な自己紹介(30秒ルール):
- 名前
- 専門分野
- 誰のどんな悩みを解決できるか
例:「税理士の田中です。中小企業の節税対策を専門に、年間100社以上のサポートをしています。今日は売上1000万円以下の会社でもすぐに使える節税テクニックをお伝えします。」
これを短く端的にまとめるだけで、視聴者はすぐに「自分に関係ある先生だ」と判断できます。
動画全体の構成テンプレート:
- 冒頭(30秒):今日のテーマと得られるメリットを明示
- 本編(5〜8分):具体的なノウハウや事例を3つのポイントに整理
- まとめ(1分):要点を再確認し、次のアクション(相談申し込みなど)を提示
さらに、各動画の冒頭に「今日は〇〇について3つのポイントを解説します」と示すことで、全体の流れが明確になり、安心して最後まで見てもらえます。これにより、動画制作のROI(投資対効果)も大幅に向上するでしょう。
【NG例3】逆効果のNG:広告っぽさ全開・自慢だらけの内容
なぜセールス色が強すぎると逆効果なのか
せっかく動画を作っても、内容が「自分の実績のアピールばかり」「商品サービスの宣伝ばかり」では逆効果です。視聴者は「売り込まれている」と感じた瞬間に離れてしまいます。
特にYouTubeやSNSの動画は、視聴者が自発的に「学びたい」「情報を得たい」という気持ちで見ています。そこに一方的な宣伝が入ると、期待を裏切られた気持ちになり、チャンネル登録の解除や低評価につながってしまいます。
士業の動画制作においては、視聴者の悩みを解決する情報を伝えることが最優先です。実績を語るにしても「自分はすごい」というアピールではなく、「こういう事例でお客様のお役に立てた」というストーリー形式で語ることが大切です。
売り込み感を与えてしまう表現パターン
以下のような表現は、視聴者に売り込み感を与えてしまう典型例です。
- 過度な実績アピール:「私は○○の案件を100件以上手がけています」
- 他者との比較:「他の事務所では対応できない案件も私なら」
- 料金の話ばかり:「うちは業界最安値で」「他社より確実に安い」
- 緊急性の演出:「今すぐご連絡ください」「限定○名様」
- 抽象的な成功談:具体性のない「おかげで成功しました」という顧客の声
これらの表現は、一見すると効果的に思えるかもしれませんが、YouTube制作においては逆効果になることが多いのです。
信頼を築く動画コンテンツの作り方
顧客視点に立って、次のような構成で動画を組み立てましょう。
1. 視聴者が抱える悩みを提示 「こんなことでお困りではありませんか?」という形で、具体的な悩みや状況を描写します。これにより視聴者は「まさに私の悩みだ」と感じ、続きを見る動機が生まれます。
例:「会社を設立したばかりで、どの書類をいつまでに提出すればいいのかわからない」
2. それを解決するための具体的なヒントや方法を紹介 抽象的なアドバイスではなく、今すぐ実践できる具体的な方法を提示します。これが動画の価値となり、視聴者の信頼獲得につながります。
例:「設立後に必要な手続きは3つあります。1つめは税務署への法人設立届出書の提出です。これは設立から2か月以内に…」
3. 実際に関わった事例をストーリーとして紹介 自慢ではなく、「お客様がどのような状況で、どんな解決策を実施し、どのような結果を得られたか」をストーリーとして語ります。
例:「先月ご相談いただいたIT企業の社長さんも同じような状況でした。設立から1か月経っても何も手続きをしていない状態でしたが、一緒に優先順位を整理し、必要な書類を段階的に提出していくことで…」
この流れを守るだけで、「この先生は信頼できる」と感じてもらえる確率が格段に高まります。
士業に特化した動画マーケティングの考え方
士業の動画制作では、一般的なマーケティング手法とは異なるアプローチが必要です。
長期的な信頼関係の構築を重視 士業は一度の取引で終わることは少なく、継続的な関係を築くケースがほとんどです。そのため、短期的な成果を求める宣伝よりも、長期的な信頼関係の構築を重視した動画制作が重要になります。
専門性の証明よりも人間性の証明 視聴者は先生の専門性よりも「この人に相談しても大丈夫だろうか」「親身になって話を聞いてくれるだろうか」という点を重視します。専門知識のアピールよりも、人柄や価値観が伝わるコンテンツ作りを心がけましょう。
まとめ:信頼される士業動画の作り方
士業の先生が動画で信頼を得るために避けるべきNGは、大きく分けて3つです。
- 暗い映像・聞き取りにくい音声:基本的な撮影環境を整える
- だらだら話して要点がない:シナリオ設計と構成の明確化
- 広告っぽさ全開・自慢ばかり:顧客視点での価値提供を最優先
これらを避けるだけで、動画は「信頼を落とすツール」から「選ばれるための武器」へと変わります。
動画は一度形にすれば長期的に働き続ける”資産”です。士業の先生こそ、動画を正しく活用することで専門性を広く伝え、顧客から選ばれる存在になれます。YouTube制作や動画制作への投資も、正しいアプローチを取ることで確実にリターンを得ることができるでしょう。
成功する士業動画の共通点
これまで多くの士業の先生の動画制作をサポートしてきた経験から、成功する動画には共通点があることがわかります。
- 継続的な投稿:月1回でも定期的に情報発信を続ける
- 視聴者との対話:コメントへの返信や質問への回答動画を作る
- 測定と改善:再生回数や視聴時間などのデータを分析し、改善を重ねる
- 他の営業活動との連携:動画を名刺代わりに活用したり、セミナーで紹介したりする
士業の先生方へ|集客を加速させたいなら動画が必須
株式会社ANDAZは、士業の先生方に特化した動画制作・YouTube制作・SNS動画制作をワンストップで提供します。
サービス内容
- 企画立案(ポジショニング戦略設計)
- 対談・セミナー・インタビュー撮影
- YouTube用長尺動画編集
- SNS用ショート動画制作
- サムネイル・タイトル設計(SEO対応)
過去には、税理士、公認会計士、弁護士、中小企業診断士など、多くの士業動画を手がけてきました。各士業ごとの特性や視聴者層を理解し、最適な形でコンテンツを制作します。
継続的に動画を更新できる仕組みを作りたいと思っている士業の先生方、ぜひともお声がけください。
一緒に、“選ばれる士業”への第一歩を踏み出しましょう!