「うちは専門職だから、動画なんて必要ない」
そう考えている士業の先生は、まだ少なくありません。
確かに、士業という職業は、知識と経験、そして資格に裏打ちされた“専門性”が評価される世界です。
しかし、いまやどんなに優れた知識や実績を持っていても、「それを伝えなければ伝わらない時代」になってきています。
かつては、ホームページに掲載されたプロフィールや文章、あるいは紹介だけで十分に仕事が得られる時代でした。
ところが、今は違います。検索する人の多くが、YouTubeやSNSなどの動画コンテンツを通じて「どんな人か」を確認し、「この人に相談してみたい」と感じたうえで問い合わせをしています。
つまり、今の時代の信頼は、「資格」や「肩書」ではなく、“伝わる人間性”によって構築されるのです。
そしてそれを一番自然に届けられる手段こそが、動画です。
動画の強みは、第一印象を一瞬で届けられることにあります。
文字や写真では伝えきれない“空気感”や“温度感”、“声のトーン”や“話し方”、“表情”や“しぐさ”といった微細なニュアンスが、画面越しにそのまま伝わります。
だからこそ、「この人は信頼できそうだ」「この先生に話してみたい」と思ってもらうには、動画が圧倒的に有利なのです。
さらに言えば、動画は“時間を節約できる営業ツール”にもなります。
事前に動画を見た人は、すでにある程度あなたの考え方やスタンスを理解した上で問い合わせをしてくれるため、初回の面談で信頼構築のステップが1つ省略されるのです。
また、今後の採用や社内ブランディングにおいても、代表者の動画メッセージは大きな効果を発揮します。
時代はすでに、動画を“選ばれる理由”に変える段階へと突入しているのです。
私たち株式会社ANDAZは、これまで多数の士業の先生方の動画制作に関わってきました。
税理士・社労士・行政書士・弁護士・コンサルタント・講師など、さまざまな分野の専門家が「動画の力」で信頼を獲得し、ファンを増やし、選ばれる存在へと進化していく姿を見てきました。
その中で気づいたのは、「うまくいく動画には共通点がある」ということです。
話す内容や撮影のテクニックよりも、もっと根本的な“視点”が存在します。
それを押さえていなければ、いくら良い機材で撮っても、魅力が伝わらない動画になってしまいます。
逆に言えば、その視点を踏まえて動画を作るだけで、
どんな先生でも“信頼され、選ばれる”コンテンツを持つことができるのです。
今回はその「士業が動画制作をする上で大切な5つの視点」を、惜しみなく公開いたします。
私たちANDAZが現場で培ってきた経験と、数々の成功事例をもとに、
“動画に不慣れな先生”でもすぐに実践できる形でお届けしていきます。
もしあなたが、「信頼をもっと可視化したい」「専門性を伝えたい」「もっと選ばれる存在になりたい」と考えているなら、
この5つの視点は、これからのあなたの強力な武器になるはずです。
それではさっそく、1つ目の視点からご紹介していきましょう!!
視点1|「信頼感」が第一印象で伝わる設計を
「この人にお願いしても大丈夫だろうか」——
士業(税理士・司法書士・社労士・行政書士・弁護士など)を探している人が、最初に感じたいのは“安心感”です。
どれだけ資格や実績があっても、「信頼できそう」と思われなければ問い合わせにはつながりません。
そしてその信頼感こそが、動画というメディアで一瞬にして伝わる最大の要素なのです。
信頼は“資格”ではなく“印象”で伝わる
「士業=信頼できる」は昔の話。
現代では、顧客側がネット検索やSNSを駆使して、複数の専門家を比較・検討する時代です。
そのなかで「この人に話を聞いてみたい」と感じさせる要素は、圧倒的に“先生の印象”に左右されます。
たとえば、同じ内容の自己紹介でも、
- カメラ目線でゆっくり話す先生
- 原稿を読み上げるような目線の合わない先生
では、信頼度に大きな差が生まれます。
動画は「声」「表情」「雰囲気」など、文字では伝えられない情報を一気に伝える媒体。
つまり、最初の3秒で「信頼できそう」と感じてもらえるかどうかが鍵なのです。
表情・話し方・服装・背景…すべてが信頼の要素
信頼感を与えるには、見た目や話し方、周囲の環境にも細やかな配慮が必要です。
士業における動画制作では、以下の4つのポイントを押さえるだけで、印象が格段に変わります。
① 表情:柔らかく、優しい笑顔を
真面目すぎて無表情になっていませんか?
笑顔には、相手の警戒心を一瞬で解く力があります。
「話しかけやすそう」「聞いてくれそう」という印象は、相談への第一歩につながります。
② 話し方:ゆっくり、落ち着いて
専門家として話すとき、つい早口になったり堅苦しくなったりしがちです。
ですが、落ち着いた口調で話すことで、視聴者に安心感を与えることができます。
また、ゆっくり話すことで、言葉の一つ一つがしっかりと伝わります。
③ 服装:清潔感と信頼感を意識して
スーツでなければならないわけではありませんが、相手が信頼を置ける印象を与える服装は大切です。
シャツの襟がよれていないか、色味が暗すぎないか、などにも気を配りましょう。
④ 背景:余計な情報は排除する
オフィスや書棚などが背景でも構いませんが、ごちゃついた印象はNG。
背景が整理されているだけで「この人は仕事も丁寧そう」と感じてもらえます。
白背景や観葉植物などを使うのもおすすめです。
カメラ目線とアイコンタクトが信頼を生む
動画で最も重要なのが、視聴者との“目線”の交差です。
実際に会って話しているわけではなくても、カメラ目線で語りかけることで、視聴者は「自分に話しかけてくれている」と感じます。
逆に、原稿を見ながら目線がズレていたり、視線が泳いでいたりすると、「この人は緊張している」「慣れていない」と思われ、信頼感が下がってしまいます。
練習が必要な部分ではありますが、カメラのレンズに向かって話すことを意識するだけで、印象が劇的に改善されます。
【視点1のまとめ】信頼感は「一瞬で伝える」時代へ
動画は、資格や実績だけでは伝えきれない「あなた自身の魅力」を伝える最適な手段です。
とくに士業においては、“正しさ”と同じくらい“安心感”を与えることが、問い合わせに繋がる大きな要因となります。
肩書や専門性だけではなく、「この人に相談してみたい」と感じてもらえるかどうか。
その第一印象を設計することが、動画活用の成否を左右します。
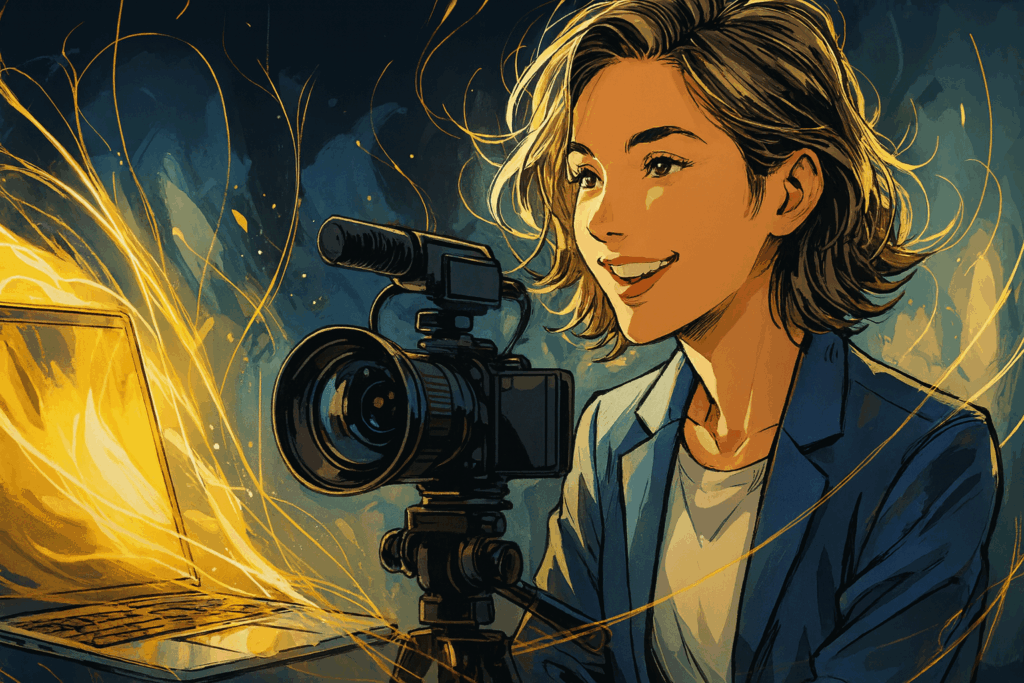
視点2|専門用語は“初心者でもわかる”言葉に変換する
動画の視聴者の多くは、あなたの普段のお仕事のジャンルに初めて触れる“初心者”だということは忘れてはいけません。
業界では当たり前の言葉を使っても((例)登記簿謄本、顧問報酬、相続登記、など)理解されないことがあります。
視点2では、専門用語について動画での取り扱いについて説明していきます。
専門用語が多いと、離脱されてしまう
初めて動画を見る人にとって、法律や制度の話は難しく感じやすいものです。
そのときに、専門用語をそのまま使ってしまうと「難しそう」「よくわからない」と感じられ、最後まで見てもらえなくなる可能性が高くなります。
たとえば、
社会保険適用拡大の対応
と話すよりも、
2024年から、パートさんも社会保険に入らないといけないケースが出てくるかもしれません
と伝える方が、視聴者には圧倒的に届きやすくなります。
専門用語そのものが悪いわけではありませんが、「その言葉が誰に向けて話されているか」によって、適切な伝え方は変わります。
初心者に向けて話す意識が、信頼につながる
動画を見る人は、基本的にその分野の“初心者”です。
だからこそ、「知らない人に伝える」という意識を持って言葉を選ぶだけで、視聴者の反応は大きく変わります。
たとえば「相続税対策」と言っても、漠然としていて意味が伝わらない場合があります。
しかし、こう言い換えるとどうでしょう。
相続税って、亡くなったあとに現金で一括で支払わないといけないんです。
都内で不動産を持っている方なら、1000万円以上になることもあります。
このように「なぜ対策が必要なのか」まで噛み砕いて説明することで、相手が自分ごととして理解できるようになります。
専門用語をわかりやすく伝える3つの工夫
① 身近な言葉に置き換える
専門的な用語を、誰でも理解できる言葉に変換する習慣をつけましょう。
「電子帳簿保存法」→「レシートや請求書も、紙ではなくデータで残さないといけない時代です」など、具体的で生活に即した表現が効果的です。
② たとえ話を使う
抽象的な制度や法律の話は、たとえ話を加えることでイメージしやすくなります。
「電子帳簿保存法って、言ってしまえば“税務のクラウド化”みたいなものです」といった言い回しは、親しみやすさと理解しやすさを両立します。
③ “この人は話がわかりやすい”という印象が残る
難しい話をやさしく伝えられる人は、それだけで信頼されます。
「この先生は、自分のレベルに合わせて話してくれる」
「何を聞いても丁寧に答えてくれそう」
こうした印象が残れば、問い合わせや契約につながりやすくなります。
専門性を、やさしく届ける姿勢がファンを生む
士業は高度な知識と正確な言葉が求められる仕事ですが、動画の中では「正確さ」と同じくらい「伝わること」が重要です。
もちろん間違った説明はいけませんが、初心者でも理解できる言葉で話すことが、結果的にあなたの専門性を正しく伝えることにもなります。
動画は、話し方・表情・雰囲気すべてが伝わる“人柄のメディア”です。
だからこそ、難しい話をやさしく伝えることで、自然と視聴者との距離が縮まり、
「この人に話を聞いてみたい」「もっと知りたい」と感じてもらえるようになります。
動画における言葉選びは、あなたの魅力を引き出すための大切なツールです。
わかりやすさを追求することで、専門家としての信頼はむしろ強化されていきます。
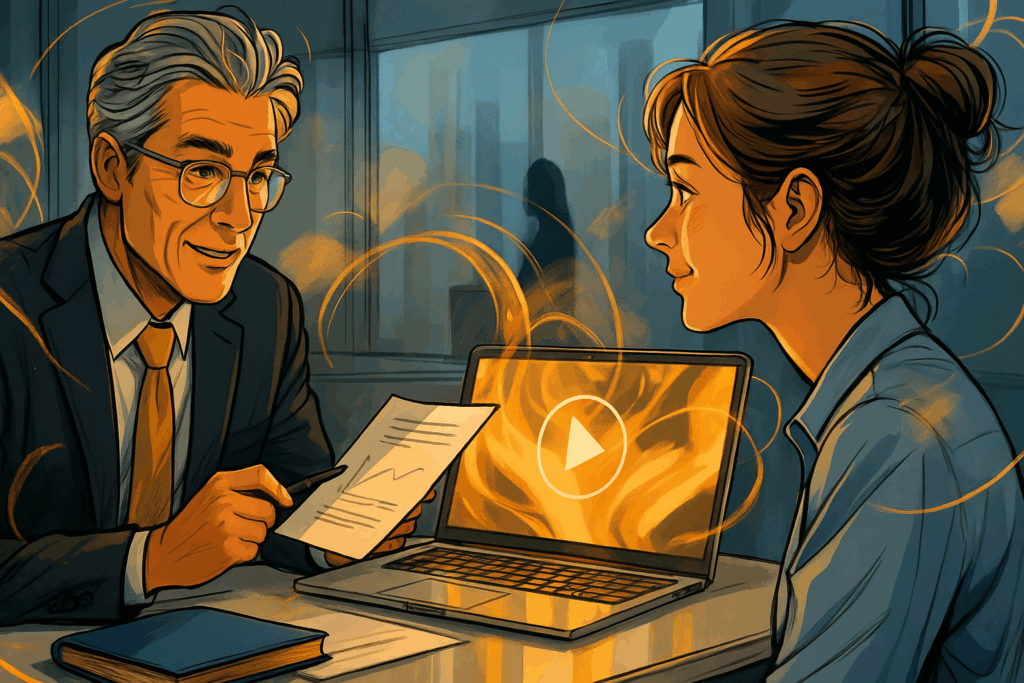
視点3|“人柄”がにじむ構成にする
動画というメディアが、他のツールと大きく違う点。
それは、「人柄」がダイレクトに伝わることです。
テキストや写真では伝えきれない、声のトーンや話し方、目線や仕草、言葉の選び方……
そういった“人間味”こそが、動画の最大の武器なのです。
特に士業の仕事は、一度きりの取引では終わりません。
顧問契約、相続、就業規則、労務トラブル、補助金対応など——
依頼者と中長期的な関係性を築く必要があるからこそ、「この人と一緒にやっていけるか?」という観点で選ばれるケースが非常に多くなります。
実績より“この人と話したい”と思われることが重要
たとえば、どれだけ資格や実務経験が豊富でも、「この人は冷たそう」「なんだか偉そう」といった印象を持たれてしまえば、問い合わせにはつながりません。
反対に、実績は少なくても「親しみやすそう」「誠実で丁寧に話を聞いてくれそう」と感じてもらえれば、相談してみようと思われます。
つまり、人柄がにじみ出る動画こそが、選ばれる士業の第一歩なのです。
この点は、士業という仕事が「感情のある人間」との対話を前提にしているからこそ、なおさら大切になります。
“先生らしさ”が伝わる構成が信頼感を育てる
では、どのようにすれば人柄を伝える構成にできるのでしょうか?
答えはシンプルです。
動画の中に、「あなた自身のストーリー」や「想い」を組み込むことです。
① なぜこの仕事を選んだのか?
たとえば、「なぜ士業の道に進んだのか」「なぜこの分野に特化しているのか」など、あなたのルーツやきっかけを話すだけで、視聴者はぐっと引き込まれます。
人は、背景を知ることで“納得”します。
単なる肩書ではなく、「そこに至るまでの物語」が見えることで、信頼と共感が生まれるのです。
② どんな思いで仕事に向き合っているのか?
「困っている人の力になりたい」
「専門知識を活かして、地域の中小企業を支えたい」
「相続で揉める家族を一人でも減らしたい」
こういった“想い”が自然と語られている動画は、視聴者の心に残ります。
士業サービスの内容は多くの人にとって似ていますが、「人の想い」には唯一無二の個性が宿るからです。
③ クライアントとの関係性について触れる
「ご相談いただいた方には、できるだけ安心して話してもらえるよう、じっくり時間を取ってヒアリングしています」
「難しい制度でも、なるべくわかりやすく伝えることを大事にしています」
このようなクライアントとの関わり方を言語化することで、「この先生なら丁寧に対応してくれそう」と具体的な安心感につながります。
タイミングは“冒頭か最後”が効果的
このような人柄を伝える内容は、動画のどこに配置するのがよいのでしょうか?
おすすめは「冒頭」か「最後」です。
冒頭に置く場合は、視聴者に“親しみ”を感じてもらいやすくなります。
たとえば、
はじめまして、〇〇士の〇〇です。私はもともと家族の相続トラブルをきっかけに、この分野に関心を持ちました。
といった一言を入れるだけで、「この人には現場目線がありそう」「相談しやすそう」と感じてもらえます。
一方で、動画の締めに軽く触れる場合は、内容を聞いたあとに「この人、いいな」と思ってもらいやすくなります。
どちらにしても、自己紹介は“ただの経歴紹介”ではなく、“思いや背景を伝える場”に変えることが重要です。
人柄は“差別化”ではなく“共感化”の鍵になる
士業の世界では、競合との差別化が難しいと言われがちです。
しかし、人柄の伝わる動画を作ることで、“専門性の違い”ではなく、“共感の違い”で選ばれるようになります。
特に、コロナ禍以降は「オンラインで会ったことのない先生に依頼する」ケースが一気に増えています。
そうした中で、動画を通じて人柄が伝わっているかどうかは、選ばれるかどうかを大きく左右する要因になっているのです。
人は、理由ではなく“感情”で動きます。
だからこそ、感情に届く動画を。
そして、あなた自身の「存在そのもの」に価値を感じてもらえるような動画を、ぜひ意識してみてください。
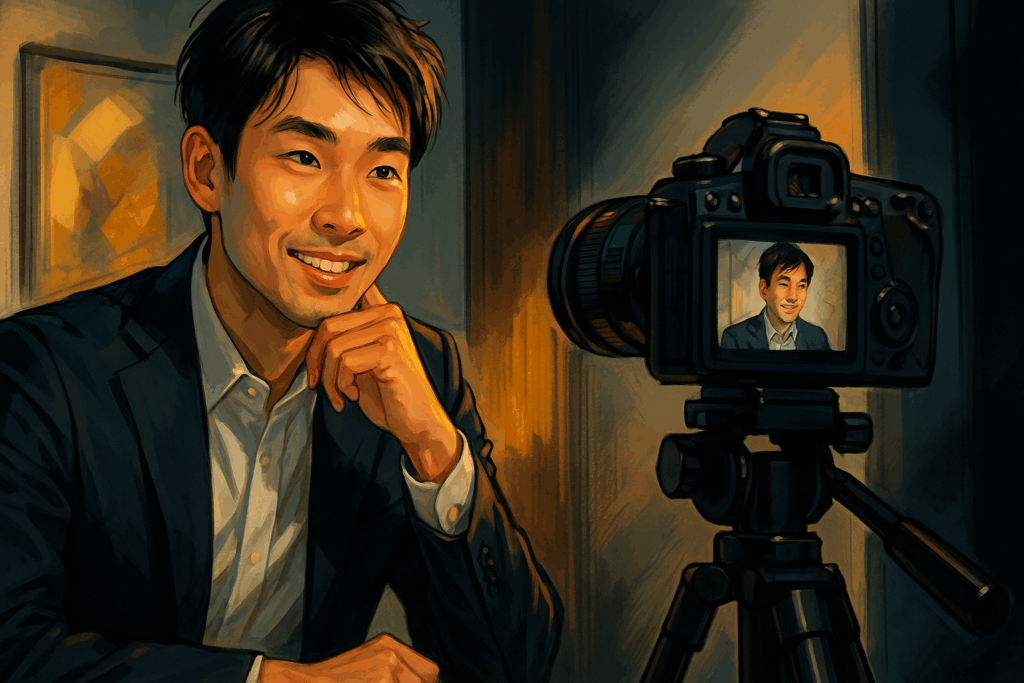
視点4|スマホ時代を意識した「短尺・テンポ・見やすさ」
スマートフォンが主流となった今、動画は“じっくり見るもの”から“すきま時間にサクッと見るもの”へと変化しています。
この流れは、士業においても例外ではありません。
「動画=YouTube」という考え方にとどまらず、InstagramのリールやTikTok、FacebookやLINEなど、様々なプラットフォームでの短尺動画が、士業の情報発信にも有効になってきています。
視聴されるかどうかは「長さとテンポ」で決まる
かつては10分・15分といった“しっかり解説する長めの動画”が主流でしたが、今の時代は違います。
3分以内で要点が伝わる動画が、多くのユーザーに好まれるようになってきました。
その理由は明確で、スマホで動画を見る人の多くが、「通勤中」「移動中」「仕事の合間」「寝る前」など、短時間で視聴できるコンテンツを求めているからです。
長くてゆったりした動画よりも、テンポよく、すぐに要点に入る動画の方が再生されやすく、離脱されにくいという傾向が顕著にあります。
(参考)
参考リンク:
Yans Media「グローバルではモバイル視聴が動画視聴の57~75%/縦型動画の視聴維持率が高い」
MMD研究所「ショート動画とコマースに関する調査」
専門職こそ“短く、的確に、伝える力”が求められる
士業の動画というと、「しっかり解説しなければ」「きちんと背景も話さないと」と、つい長尺になりがちです。
もちろん、そうした丁寧な解説が必要な場面もありますが、まずは“関心を持ってもらう入り口”としての動画を用意することが大切です。
特に以下のようなテーマは、短尺動画との相性が抜群です。
- 「知らないと損する補助金制度、3つのポイント」
- 「社労士が語る、労務トラブルを防ぐひと言」
- 「相続相談でよくある質問、トップ3」
こうした切り口なら、1〜3分以内で十分にまとめることができ、視聴者にとっても「ちょっと見てみようかな」と思ってもらえます。
見られる動画には3つの条件がある
① 短い
「結論まで時間がかかる動画」は、スマホ時代には好まれません。
特に冒頭の10秒で興味を引くことができなければ、そのまま離脱されてしまう可能性が高くなります。
最初に要点を提示し、そのあとに補足や背景を説明する構成にすることで、離脱率を大きく下げることができます。
② テンポがよい
動画のテンポは、視聴者の集中力を左右します。
士業の場合、落ち着いた話し方が信頼感を生む一方で、テンポが遅すぎると“退屈”に感じられてしまうことも。
適度なスピードで、区切りよく話すことで、メリハリのある動画になります。
字幕や効果音、図解の挿入などを加えると、よりテンポよく、見やすさが向上します。
③ スマホで見やすい
動画のフォーマットは、いまや縦型(9:16)が主流です。
YouTube ShortsやInstagramリール、TikTokなど、主要なプラットフォームがすべて“縦画面”に対応しているため、スマホ1台で手軽に視聴されやすい設計が求められます。
また、音声を出せない環境でも理解できるように、字幕の表示も非常に重要です。
電車の中やオフィスなどで、ミュート再生されることを前提に設計しましょう。
短尺動画は“関心の入り口”として最強のツール
士業が短尺動画を活用する最大のメリットは、「専門的な話を簡潔に伝えられる」「関心のある人を引き込むことができる」ことにあります。
そして、一度動画を見た人は、あなたの話し方や雰囲気に触れ、“人柄”と“信頼感”をセットで感じてくれるようになります。
その結果、
- 「この先生、わかりやすかったから相談してみたい」
- 「ほかの動画も見てみたい」
- 「同じような悩みを持っている友人に紹介したい」
といった行動へとつながり、ファン化・集客・信頼構築へと波及していきます。
“スマホ時代に最適化された動画”が、あなたを選ばせる
現代の動画視聴の9割以上は、スマートフォンから行われていると言われています。
だからこそ、動画制作の際は「パソコンで見られること」ではなく、「スマホで見られること」を最優先に考える必要があります。
短く・テンポよく・見やすく。
そして、自然と人柄と価値が伝わる構成に。
これが、スマホ時代における士業動画の「勝てる設計図」です。
(株式会社ANDAZが制作した士業の縦型動画の制作例)
視点5|「動画の置き場所と導線」を戦略的に設計する
せっかくプロの力を借りて、時間とコストをかけて良い動画を作っても、それが誰の目にも触れなければ意味がありません。
動画の効果は「作ったあと」に決まると言っても過言ではありません。
士業のビジネスにおいて、動画は集客・信頼構築・教育・ブランディングなど多くの目的に活用できますが、「どこに置くか」「どう見てもらうか」といった導線設計が不十分だと、本来の価値が発揮されません。
なぜ「動画の置き場所」が重要なのか?
視聴者が動画を見るタイミングには「自分で探して見つけるパターン」と、「自然と目に入って見るパターン」の2種類があります。
士業が動画を使って情報発信を行なっていくには、意図的に後者の、将来のクライアントが「SNSを回遊してる際に、自然と目に入って見るパターン」を設計することが成功の鍵になります。
ホームページやLPに訪れる人は、すでにある程度興味を持っている状態。
その人に対して、「文章だけで判断させる」のに加えて+「動画でファンになってもらって」から、問い合わせをしてもらうのとでは、その後の成約率が大きく変わってきます。
おすすめの動画設置ポイント
① ホームページのトップページ
最も効果的なのは、ホームページのファーストビューに動画を設置することです。
「こんにちは、〇〇士の〇〇です。私はこんな思いで活動しています——」という30秒〜60秒程度の自己紹介動画があるだけで、離脱率が大きく下がります。
ファーストビューにある動画は、「見よう」と意識しなくても目に入るため、自然な接触が生まれます。
② 自己紹介ページ(プロフィール)
「この先生はどんな人だろう?」と興味を持った人が必ず訪れるのがプロフィールページです。
ここに動画があると、文字では伝わらない雰囲気や人柄まで伝えることができ、「この人にお願いしたい」と思ってもらいやすくなります。
特に初めて士業を利用する人や、複数の専門家を比較検討している人にとっては、動画による印象が決定打になることも少なくありません。
(株式会社ANDAZが制作した士業のHPに自己紹介動画を掲載して成約率を上げている例)
https://paradigmshift-llc.com/company
③ お問い合わせ・相談ページ
相談フォームのページに「よくある質問に答える動画」や「初回面談の流れを解説する動画」などを配置すると、不安や疑問を事前に解消できる導線になります。
結果的に「問い合わせ前に納得できた」「この先生なら信頼できる」と感じてもらえるため、質の高いリード獲得につながります。
SNSやLINE、メルマガにも「動画導線」を
ホームページだけでなく、SNSやLINE、メルマガなど“情報を届ける手段”にも動画は有効です。
特に以下のような活用が効果的です。
① LINE公式アカウント
ステップ配信の1通目やプロフィール欄に、「代表の自己紹介動画」や「サービス案内動画」を入れておくことで、登録者との距離を一気に縮めることができます。
② メールマガジン
文章の中に動画へのリンクを差し込むことで、「読む」だけでなく「見る」という行動を促すことができます。
特に、専門的なテーマを扱う回には「補足解説動画」を入れると、離脱率が下がり、理解度も深まります。
③ Instagram・YouTube・TikTok
各SNSで発信しているショート動画や解説動画は、単体で終わらせず、ホームページやLINEなどへの導線を設計することで、見込み客の囲い込みができます。
導線設計のコツは「初めての人目線」で考えること
動画を「どこに置くか」を考えるとき、最も大切なのは“初めてあなたのサービスを知る人”の目線に立つことです。
- 初めてホームページを開いたとき
- SNSのリンクから飛んできたとき
- メールを開いたとき
こうした“入口”に近い場所に動画を設置することで、「見てもらえる確率」が圧倒的に高くなります。
逆に、「動画一覧ページにまとめてある」など、クリックしないと辿り着けない設計だと、多くの人がたどり着けないまま帰ってしまいます。
あなたの動画は、ちゃんと「見られる場所」にありますか?
動画は、ただ作るだけでは意味がありません。
「誰に、どのタイミングで、どうやって見せるか」という設計こそが、動画活用における真の勝負どころです。
配置場所と導線を戦略的に設計することで、動画が“営業マン”として機能し、信頼と集客の起点になります。
これまでに動画を作ったことがある方も、これから動画を活用していきたい方も、まずは「動画を見てもらうための導線設計」から見直してみてください。
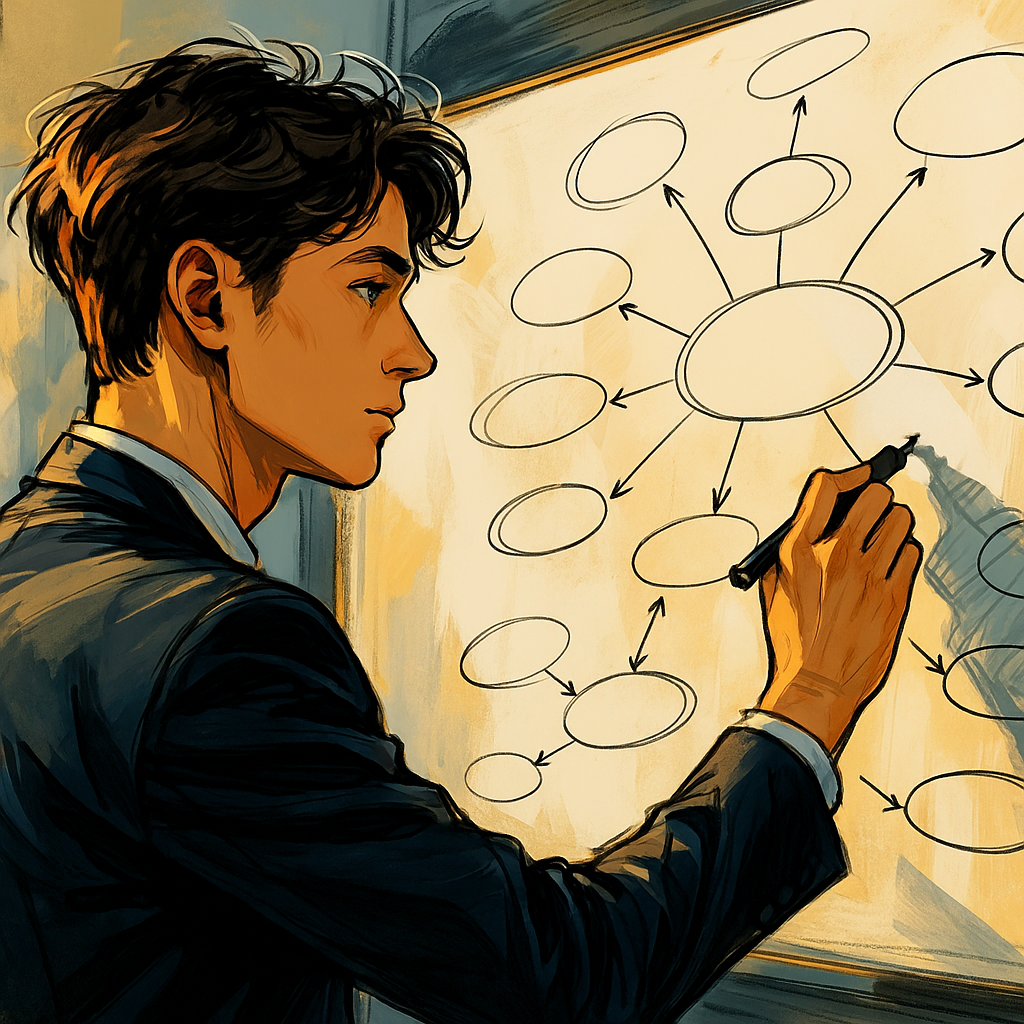
まとめ|“選ばれる士業”は、伝え方まで設計している
どれだけ知識や経験が豊富であっても、
それを「伝える力」がなければ、見込み客には届きません。
どれだけ真摯な想いがあっても、
それが「伝わる形」に整えられていなければ、共感にはつながりません。
今、選ばれる士業に共通しているのは、
“伝え方”を意識して設計しているかどうかです。
士業こそ、「伝える力」が問われている時代
かつて、士業は「信頼=資格+実績」で成り立っていました。
しかし、今は違います。
スマートフォンひとつで専門家を検索し、比較し、選ぶ時代。
ユーザーが最初に判断するのは、肩書や経歴よりも“印象と雰囲気”です。
特に顧問契約や相続・労務など、長期的な関係を前提とするサービスでは、
「この先生と話してみたい」「この人なら信頼できそう」
そんな“感覚的な安心感”が、最初のアクション(=問い合わせ)につながります。
その安心感を届ける最適な手段が、動画なのです。
動画は、信頼・知識・想いを「濃く・深く・瞬時に」届ける
動画のすごさは、1分間に約180万語分の情報を伝えると言われるほど、情報量が圧倒的に多いこと。
表情・声のトーン・間・雰囲気・服装・空気感…。
それらがすべて「非言語のメッセージ」となって、視聴者に届きます。
だからこそ、文章では伝えきれなかった“あなたらしさ”が、動画では自然ににじみ出てきます。
つまり、動画はあなたの「魅力を可視化するツール」であり、
その魅力が“信頼”や“選ばれる理由”に変わっていくのです。
5つの視点を押さえれば、初心者でも安心して始められる
今回お伝えした5つの視点は、どれも士業が動画を活用するうえで“本当に大切なポイント”です。
- 第一印象で信頼を感じさせる設計
- 専門用語を初心者にもわかりやすく翻訳する力
- 人柄が自然と伝わる構成
- スマホ時代に最適化された短尺・テンポ・見やすさ
- 見てもらえるための動画配置と導線の戦略設計
この5つの視点を押さえるだけで、動画は単なる「撮っただけのコンテンツ」から、
あなたのビジネスを支える「最強の営業マン」へと進化します。
伝える内容ではなく、「伝わる形」に整えること
士業の先生方が伝えたい内容は、どれも本当に価値ある情報ばかりです。
でも、それが専門的すぎたり、難しかったり、届きにくい場所に置かれていたりすると、
どれだけ素晴らしい内容でも“スルー”されてしまうのが現実です。
だからこそ、「伝わる形」にプロデュースすることが重要です。
- 誰に向けて、何を、どの順番で話すのか
- どんな雰囲気で、どんな言葉で語るのか
- どこに配置して、どう見せるのか
こうした“見えない設計”の部分にこそ、動画の成果を大きく分ける分岐点があります。
あなたの魅力を、動画という「かたち」に
私たち株式会社ANDAZは、これまで多くの士業の先生方の動画をプロデュースしてきました。
そして確信しています。
伝え方が変われば、反応が変わる。
反応が変われば、売上も信頼も自然と変わっていく。
動画の目的は、ただカッコよく仕上げることではありません。
「あなたという存在の価値が、初対面の人にも正しく伝わること」
それが、本当に成果につながる動画なのです。
あなたのストーリーを、世界に伝えませんか?
もしあなたが今、「動画を活用してみたいけれど、何をどうすればいいかわからない」
あるいは、「動画はあるけれど、効果が実感できていない」と感じているなら——
それは、あなたに魅力がないのではなく、
魅力の伝え方が最適化されていないだけかもしれません。
“選ばれる士業”には、選ばれるための設計があります。
そして、その設計を一緒につくるのが、私たちANDAZの役割です。
動画は、単なるコンテンツではありません。
それは、あなたの魅力と信頼を社会に届ける、ストーリーテリングの手段です。
いまこそ、「伝えること」に本気になってみませんか?
あなたの想い、知識、人柄を、
動画というかたちにして——
一緒に、“選ばれる士業”への第一歩を踏み出しましょう!

最後に(撮影受付について)
私たち株式会社ANDAZでは、士業専門の動画制作を承っております。
✔️ 弁護士・税理士・行政書士・社労士などの先生業に特化
✔️ 台本構成〜撮影〜編集までワンストップ対応
✔️ SNS用の短尺動画やリールも対応可能
先生業の動画は、ぜひANDAZにお任せください。
「士業の先生の魅力を、もっと世の中に。」
あなたの想いに、映像という翼を──。

